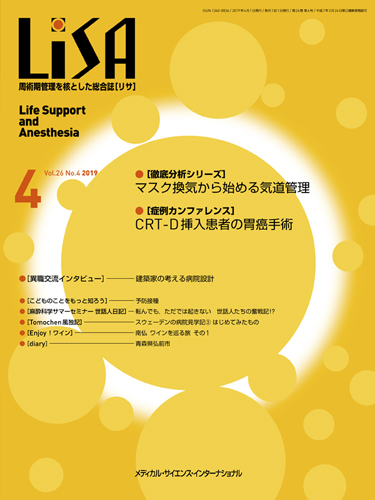ロボット麻酔という言葉が一人歩きしている。
ロボットが麻酔をする?ロボット手術の麻酔?いずれでもない。
ロボット麻酔とは、Robotic Anesthesiaを日本語表記したものである。
Robotic Anesthesia – A Vision for the Future of Anesthesia - PMC (nih.gov)
麻酔をするロボットといわれて簡単に思いつくのは、麻酔薬を自動投与してくれるもの、気管挿管をするロボットであるが、前者はPhermacological Robots、後者はManual Robotsと呼ばれる。今回、日本光電社がライセンス販売を開始したのは、前者に相当するもので、closed-loopシステムにもとづくPhermacological Robotsのソフトウェアである。ここで、???となるのだが、なぜソフトウェアなのか。機械はなくても動くのかということである。答えはNOである。
必要なハードウェアは、ソフトウェアをインストールして動かすためのPC(Windows)、シリンジポンプ(テルモ社製スマートポンプ限定)3台、日本光電社製生体情報モニター(BISモニター、筋弛緩モニター含む機種限定)とそれぞれを接続するケーブルが必要である(これらは別途に用意する必要がある)。使用する薬剤は、プロポフォール、レミフェンタニル、ロクロニウムが必要で、それぞれシリンジポンプに載せて持続投与する。現在のところ、この3つの薬剤の組み合わせ以外は使用できない。
薬剤のコントロールは、筋弛緩薬ロクロニウムの効果を筋弛緩モニター(日本光電社製)でモニタリングしてclosed-loop制御で投与量を調節する。プロポフォールやレミフェンタニルはBISが45となるように決められたアルゴリズム(closed-loop制御)で調節をおこなうものである。つまり、麻酔中の鎮静度、筋弛緩状態のデータをフィードバックすることで筋弛緩薬、鎮静薬、鎮痛薬の投与量を自動調節する。
しかし、血圧や脈拍、呼吸数や換気量、SpO2、EtCO2、気道内圧、体温などは、生体情報モニターに表示はしているが何の保障もない。また、出血、尿量、術野の状況なども考慮されていない。したがって、患者状態をコントロールするためには、このシステムに慣れた麻酔科医がその場にいて介入する必要がある。自動車で言えば、高速道路を安定走行しているときのオートクルーズボタンと思えば良い。車を運転できる能力が必要である。もっと言えば、オートクルーズがはずれたときに、自分で運転できない人は使えない。
自動運転にもレベル0からレベル5までの段階がある。レベル1とレベル2は人が主体で、運転支援といわれるもの、レベル3からレベル5が車が主体で、程度の差はあれ自動運転と呼べるものである。
https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf
今回のシステムは、自動運転のレベル1か2だと考えられるため、運転支援のレベルと言える。
さて、次に気になるのは、誰がこのシステムを操作できるのかということである。
日本麻酔科学会の全身麻酔用医薬品投与制御プログラムに関する適正使用指針<2023年3月制定>
に、その答えがある。
「使用可能な医師の条件」として
(1)日本麻酔科学会あるいは日本専門医機構の麻酔科専門医、日本麻酔科学会の麻酔科指導医で、過去にTIVA管理症例が300例以上あることが証明できる医師
かつ
(2)この製品プログラムのトレーニングコースを修了している医師
である。
「使用可能な施設」にも以下の3つの条件がそろっている必要がある
(1)日本麻酔科学会の麻酔科認定病院として認定されていること。
(2)日本麻酔科学会の年次報告で過去 3 年間の麻酔科全身麻酔管理症例の 50%以上あるいは年間 600 例以上の全静脈麻酔(TIVA)管理症例があること。
(3)日常的に使用する全手術室に脳波モニターおよび筋弛緩モニター(神経刺激装置は不可)が常備されていること。
また、「使用できる患者」にも
ASA-PS 分類 2 以下の成人患者(低体温療法での手術、心臓血管外科の手術、妊娠中の患者を除く)という制限がある。
さらに、本システムを使用している間は、「使用可能な医師の条件」を満たす麻酔科医師が当該手術室内に常駐すること。いかなる理由があっても、医師以外のメディカルスタ ッフに麻酔管理を担当させないこと(全身麻酔の導入から麻酔を行う本システムによ る麻酔は絶対的医行為と見なされるため)。
いかがだろうか。
経験のある麻酔科医がプロの道具として使うとき、その真価が発揮されると考える。
せっかくの夢のあるシステムも正しい条件下で使用しなければ、その先はない。
これまでに、Sadasys(R)なども米国では発売されたが、鎮静を仕事にする麻酔看護師が使わない作戦を展開して売れずに製造が中止された経緯がある。
日本では、どの様な反応が起きるのだろうか。
まさか、これで麻酔科医が不要と考える人はいないと思うが、このシステムを導入して十分に使いこなせない人に麻酔を担当させ麻酔事故をおこすことは断じて許さない。
このシステムがSedasysの様にならないように、うまく発展させて麻酔科医の味方につけたいと思っている。

ミズチバの話題が再燃している。ミズチバとは、アルチバ(レミフェンタニル)を溶解するのを忘れて、溶解液のみを注射器に詰めて用意することをさす。
アルチバの入った注射器であると思っていたら溶解液だけだったという場合、すなわち、水をアルチバと思って投与することから作られた造語である。これは、全国区の言葉である。
これと同様の造語に、ユカチバがある。ユカチバはアルチバの注射器をシリンジポンプにセットして、輸液ラインに接続し忘れてポンプのスタートボタン押したときに床にポタポタと落ちる様を表す言葉である。また、アルチバを溶解した後に、注射器内の空気を取り除こうとして勢い余って床にアルチバがこぼれて様子を表すこともある。
それ以外に、
ウスチバというのもある。これは意図的に行われることが多い。アルチバを溶かす際に、こぼしてしまったため、さらに溶解液で希釈してシリンジポンプにセットしている状態を指す。これは、「今日のアルチバは効きにくい」と指導医が言葉を発したときに、希釈した者がその真相を明かさなければ決してばれない。希釈現場を目撃されている場合は、話は別である。
ユルチバもユカチバと同様の意味だが、シリンジとエクステンションチューブあるいは輸液ルートとの接続が緩んでいて、アルチバが漏れている状態を指す。ロックつきでない注射器にエクステンションチューブを使用していると起こりやすいが、ロック付きを使っていてもきちんと閉めないとおきることがある。
トメチバというのは、エクステンションにクランプがついているモノや3方活栓を使っている場合に起こりうる。クランプをはずさすに注入を開始するか3方活栓を開けずに注入を開始した場合に起きる。この場合には、シリンジポンプのアラームが鳴って気づく。また、アルチバの効果が強く出て、シリンジポンプを一時停止した場合に、止めていたことを忘れている場合にも使う言葉である。シリンジポンプは、2分間停止しているとアラームが鳴るのであるが、たまたま、そのとき周りが騒々しくて音が聞こえない場合、さらに長時間停止していることに気づかないこともある。
ウソチバというのは、ガンマ計算(管理人はガンマは口語であると思うのだが、テルモのシリンジポンプには堂々と表記してある。)つきのポンプで投与した場合、1mg/mlの希釈数値以外、あるいは体重kgを誤って入れた場合に起きる投与速度の誤りである。たとえば、体重80kgを8kgと入力した場合、投与速度はガンマの値を信用して入力すれば1/10の投与速度になってしまう。
カラチバというのは、ミズチバとと同じ意味を表すこともあるが、別の意味もある。シリンジ混入した空気をきちんと追い出さずにポンプにセットした場合、最後は空気を押していることになる。大抵はエクステンションチューブ内で空気は止まるので患者には入らないが、その後が問題である。次のアルチバをセットするときに、エクステンション内の空気を抜くのに時間がかかり、手間取ることが多い。ご存じの通り、アルチバの半減期は短いため、すぐに血中濃度が下がっていく。ぎりぎりの濃度で麻酔をしている場合には、慌てることになる。トラブルが起きるからといって不必要に高濃度で行うのも問題ではあるが。。。。
さらに
もつかわれている。
コイチバというのは、思いがけず一本の注射器に2本のアルチバを溶かしてしまうことをさす。よくあるのは、一本しているときに、誰かに話しかけられてもう一本希釈してしまう状況である。また、意図的に通常(100μg/mL)の2倍の濃度にする場合にも使われる。「これ、コイチバだからいつもの半分の速度で投与しています」などとつかう。
オオチバというのは、意味が2つある。ひとつはアルチバの投与速度が速いことをさし、「それ、オオチバじゃない?」という。この場合には、ハヤチバともいう。「それ、ハヤチバだろう。そんなにいる?」などとつかう。もう一つの意味は、大きいアルチバ=5mgのアルチバをさす言葉である。「うちのはオオチバだから、50ccに希釈してね」などとつかう。この意味で使われる言葉にデカチバもある。
コチバというのは、オオチバの反対で2mgのアルチバのことである。チビチバともいう。
ギザチバというのは、アルチバの速度を頻回に変更して使っていることを言う。血圧が上がればアルチバの投与速度を上げ、血圧が下がればアルチバの投与速度を下げるような状況が延々と続いていることを示す言葉である。どちらかというとアルチバの使い方が下手なことを意味する。
ナイチバというのは、全身麻酔を覚醒させる際にアルチバの血中濃度(効果部位濃度)をゼロにする(効果が無視できるほど下げる)ことをいう。「はやめにナイチバにして、呼吸をだしてから覚醒させなさい」などと使う。この場合、早めにやめることを指してヤメチバともいう。
いろいろ、チバ類を紹介したが、ミズチバは麻酔科医には最も恐れられているものである。
ミズチバをひきおこすと、とても不幸な結果となるため、予防が大切であることは言うまでもない。

2021年6月25日(金)〜27日(日)に沖縄県名護市の万国津梁館で第17 回麻酔科学サマーセミナーを開催します。本来は、2020年6月25日〜27日に第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会に引き続き開催する予定でしたが、第17 回麻酔科学サマーセミナーは2021年6月25日〜27日に延期いたします。第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会は、同時開催ではなく2021年2月25日(木)〜26日(金)に日程を変更いたしました。
第17 回麻酔科学サマーセミナーの2021年6月25日のイブニングセミナーでは、いつも盛り上がるi-gelのセミナーが、最終日の6月27日のモーニングセミナーでは、意識下挿管のセミナーが決定しています。恒例企画であるバトルオンセミナー(6月26日)のテーマとして「2台持ち時代のビデオ喉頭鏡」に3社以上の参加が予定されています。一般演題は、研修医セッション(平成28年度以降に卒業の医師対象)と一般セッション(医師およびコメディカル対象)に分けて募集しますが、いずれも6月27日夕方の発表となっています。それぞれ優秀演題には賞状および副賞が贈られます。
第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会では、2月25日のイブニングバトル「麻酔効果のモニタリング」では、筋弛緩モニター/術中処理脳波モニター 4-5社が共催して行うテクノロジーまたは臨床応用に関するセミナー(バトル)が予定されています。モーニングシンポジウム(2月26日)「自動麻酔記録から自動麻酔へ」では、現実的になりつつある自動麻酔に関する期待や問題点について、本音で討論いただきます。同日のランチョンセミナーでは、全身麻酔中の侵害受容刺激反応レベルのモニタリングに関する講演を予定しています。午後からは、麻酔科医療に役立つウェアラブルコンピューティングをテーマに、ウェアラブルの伝道師である塚本昌彦先生に基調講演をお願いしています。引き続き、公募シンポジウムを行います。一般演題(口演)と機器展示ブースでのラウンドセッション(機器展示ブースを巡りショートプレゼンを聴く全員参加ツアー)も6月26日に行われます。一般演題のポスターセッションは、中止し、すべて口演とします。一般演題では優秀演題が選出されます。機器展示ブースでのラウンドセッションでも、最優秀プレゼンテーションには、賞状と副賞が贈呈されます。それ以外にも、会長または審査員が学会会期内に際立った能力を認めた場合には、特別賞として賞状および副賞を贈呈します。
テクノロジー学会は、すでに早期参加登録を開始し2020年11月9日(月)までがお得です。いずれの学会の参加登録を完了した場合にもお得な価格でブセナテラスの宿泊予約を提供する予定です。
宿泊と飛行機の予約をお早めに!

2020年6月26日〜28日に沖縄県名護市の万国津梁館で第17 回麻酔科学サマーセミナーを開催します。今年は、6月25日〜27日に第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会を同会場で開催いたします。両学会の合同企画として、写真コンテストとアイデアコンテストを開催いたします(いずれもどちらかの学会に参加の場合に応募可能です。いずれのコンテストにも賞状と副賞を用意しています)。参加費に関しても、第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会で1人あたり11000円以上支払われた場合には、第17回麻酔科学サマーセミナー会費の割引を設定しました。さらに、いずれの学会も、平成28年度(2016年度)以後に卒業した医師に研修医価格を設定しました。
第17 回麻酔科学サマーセミナーの6月26日のイブニングセミナーでは、いつも盛り上がるi-gelのセミナーが、最終日の6月28日のモーニングセミナーでは、意識下挿管のセミナーが決定しています。恒例企画であるバトルオンセミナー(6月27日)のテーマとして「2台持ち時代のビデオ喉頭鏡」に3社以上の参加が予定されています。一般演題は、研修医セッション(平成28年度以降に卒業の医師対象)と一般セッション(医師およびコメディカル対象)に分けて募集しますが、いずれも6月27日夕方の発表となっています。それぞれ優秀演題には賞状および副賞が贈られます。
第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会では、6月25日のイブニングバトル「麻酔効果のモニタリング」では、筋弛緩モニター/術中処理脳波モニター 4-5社が共催して行うテクノロジーまたは臨床応用に関するセミナー(バトル)が予定されています。モーニングシンポジウム(6月27日)「自動麻酔記録から自動麻酔へ」では、現実的になりつつある自動麻酔に関する期待や問題点について、本音で討論いただきます。同日のランチョンセミナーでは、全身麻酔中の侵害受容刺激反応レベルのモニタリングに関する講演を予定しています。午後からは、麻酔科医療に役立つウェアラブルコンピューティングをテーマに、ウェアラブルの伝道師である塚本昌彦先生に基調講演をお願いしています。引き続き、公募シンポジウムを行います。一般演題(口演)と機器展示ブースでのラウンドセッション(機器展示ブースを巡りショートプレゼンを聴く全員参加ツアー)も6月26日に行われます。一般演題のポスターセッションは、6月27日のサマーセミナーのポスターセッションと同時間帯に発表を行う予定です。一般演題では口演、ポスターのそれぞれから優秀演題が選出されます。機器展示ブースでのラウンドセッションでも、最優秀プレゼンテーションには、賞状と副賞が贈呈されます。それ以外にも、会長または審査員が学会会期内に際立った能力を認めた場合には、特別賞として賞状および副賞を贈呈します。
テクノロジー学会は、2019年12月から早期参加登録を開始しています。サマーセミナーは、2020年1月には早期参加登録を開始予定です。
いずれの学会の参加登録を完了した場合にもお得な価格でブセナテラスの宿泊予約が可能になっています。
宿泊と飛行機の予約をお早めに!
第15回 麻酔科学サマーセミナー 世話人日記
転んでも,ただでは起きない
世話人たちの奮戦記!?
麻酔科学サマーセミナー世話人 讃岐 美智義
をLiSA 2019年 4月号 にかきました。
はじめはイニシャルトークにしていたのに、世話人達は実名で問題なーい!!
ということで、実名表記になっています。
2018年6月29日(金)〜7月1日(日)+ 延長滞在
の顛末を世話人日記として赤裸々に詳述しました。
ぜひ、ご一読ください。
の参加登録、演題募集も始まりました。今年もやります。
多数のみなさまのご参加をお待ちしています。
2019年6月28日(金)~30日(日)

沖縄科学技術大学院大学(OIST)
カンファレンス・センター 講堂
〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919-1

2019年4月1日(月)~5月8日(水)
LiSA 2019年4月号/(MEDSi)株式会社 メディカル・サイエンス・インターナショナル